ぐるっと流山 令和7年度生物多様性シンポジウム

令和7年9月14日(日曜日)、おおぐろの森中学校と大畔の森で「令和7年度生物多様性シンポジウム」が開催され、小学生とその保護者19組48名が参加しました。このイベントは、環境学習を通して生物多様性の重要性について学んでもらうとともに、生物多様性の保全・回復に優先的に取り組むために選定された重点地区・拠点の魅力を知っていただくことを目的として、市が生物多様性に知見のある団体に委託し、毎年開催しています。
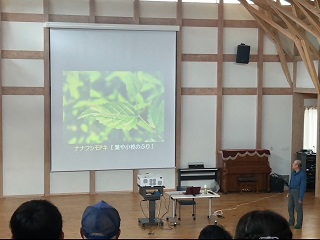
初めに、元千葉県立流山おおたかの森高等学校の生物教諭で、ナチュラリストとして活躍する山田純稔さんから、「里山は生き物の不思議がいっぱい!ー学んで、見つけて、つながる命ー」と題して講演がありました。食べる、食べられるで生き物の関係は繋がっていること、木や草の種類が多いと虫の種類も多く、虫の種類が多いと虫を食べる生き物の種類が多く、生き物の豊かな里山になると山田さんからお話がありました。
虫は小さな生き物のため、鳥などの大きな生き物には敵いません。食べられないようにするために、虫は工夫をしています。枯葉のふりをするアケビコノハ、鳥の糞のふりをするオカモトトゲエダシャク、目玉の模様で鳥から身を守るコジャノメなど、見つからないように体を隠したり、目立つ形や模様で身を守ったり、毒を持ったふりをしたり、他の虫に守ってもらったり、生き残るために様々な工夫をしているとお話がありました。

講演の後は、大畔の森で生き物を探しました。生き物を捕まえた後、山田さんと里山ボランティア流山の若林さんと渋谷さんの3つの班に分かれて、捕まえた虫などの解説がありました。山田さんの班はトンボやイナゴの見分け方、コオロギの生活やカマキリと寄生虫などについて、若林さんの班はトンボやバッタの性別の違い、アゲハの口のしくみなどについて、渋谷さんの班は虫の冬の過ごし方や触角と夜のくらしなどについて解説がありました。

その後、捕まえた生き物のうち、一番印象に残った生き物を各班で発表しました。山田さんの班はオオシオカラトンボ、若林さんの班はジャコウアゲハの幼虫、渋谷さんの班はニホンアカガエルでした。ニホンアカガエルは千葉県の最重要保護生物です。
最後に、山田さんから「現在の環境を維持しつつ、草地や林縁をモザイク状に残すなど小さな工夫を積み重ねれば、より多様な生き物が暮らせる豊かな森になるので、今後もみんなで見守り保全に努めましょう」とお話しがありました。その後、捕まえた生き物が森に帰っていく様子を全員で見送りました。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
